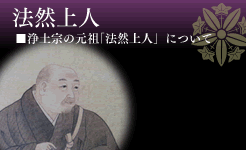私ども浄土宗の宗祖は法然上人です。
来たる2011年はちょうど「800回忌」にあたります。
ここで改めて法然上人について、そのご一代と、
法然上人の教えについて紹介いたします。
法然上人のご一代。
<お生まれと父上の遺言>
 法然上人は、1133年に、現在の岡山県・津山市の近くでお生まれになりました。父君は押領使(おうりょうし)(今でいう警察署長)で、名は漆間(うるま)時国(ときくに)といいました。母君の名前は不詳ですが、秦氏(はたうじ)のご出身です。従って法然上人は武士の子であり、しかもご夫妻の「一粒種」でありました。ご夫妻の、聡明で立派な人に育ってほしいという願いから、勢至菩薩(せいしぼさつ)にあやかって勢至丸(せいしまる)という名がつけられました。
法然上人は、1133年に、現在の岡山県・津山市の近くでお生まれになりました。父君は押領使(おうりょうし)(今でいう警察署長)で、名は漆間(うるま)時国(ときくに)といいました。母君の名前は不詳ですが、秦氏(はたうじ)のご出身です。従って法然上人は武士の子であり、しかもご夫妻の「一粒種」でありました。ご夫妻の、聡明で立派な人に育ってほしいという願いから、勢至菩薩(せいしぼさつ)にあやかって勢至丸(せいしまる)という名がつけられました。
勢至丸さまが9歳になられた春のこと、父上が夜討ちに遭われます。今わの際(きわ)に、「おまえは武士の子ゆえ、敵を討とうと思うであろうが、そうすれば今度は彼の子がお前を敵と狙うであろう。怨(うら)みは新たな怨みを呼ぶだけだ。それよりも出家して、父の菩提(ぼだい)を弔ってくれるとともに、誰もが平等に救われていく道を求めてほしい。」と、勢至丸さまに遺言なさいました。ここに勢至丸さま(後の法然上人)の出家の縁があるのです。
<政情不安、末法の世>
ところで法然上人ご在世当時の世情はといいますと、四百年近く続いた平安時代も終焉(しゅうえん)の時期に入っていて、為政者は国民のことはそっちのけで権力闘争に明け暮れ、骨肉(こつにく)相食(あいは)むという極めて悽惨(せいさん)な様相を示しておりました。それゆえ「物(もの)の怪(け)」や「怨念(おんねん)」の祟(たた)りを恐れるといった風潮が蔓延(まんえん)し、社会情勢はたいそう不安定で、人々の生活は困窮を極めていました。いわば「世も末」であったわけです。加えてこの時期は仏教でいう「末法(まっぽう)」の時代に入ったと信じられていました。
従って、父君・時国公の遺言は単に勢至丸さま個人の問題にとどまらずして、広く日本全体に当てはまることであったのです。
<比叡登山と浄土宗開宗>
このような「課題」を解決すべく、勢至丸さまは、当時の仏教の中心地・比叡山へ修行に上られることとなりました。そして師事されたお師匠さまから、「源空法然(げんくうほうねん)」という僧名を頂かれます(これを略して私たちは法然上人と呼んでいます。なお上人(しょうにん)というのは、僧侶に対する敬称です)。求道・研鑽に励むこと三十有余年、ついに、だれもが平等に救われる道を経典の中に探し当てられました。それが「念仏の教え」だったのです。時に御年(おんとし)43歳のことで、「浄土宗開宗の年」とされています。
これを機に、法然上人は比叡山をお下(お)りになり、現在の円山公園あたりに庵(いおり)を結ばれました。そして京都を中心に、広く念仏の教えを説き勧められることとなったのです。
<広がる念仏の教えと80歳ご往生>
念仏を称えることにより、今生(こんじょう)を終えた後、凡夫(ぼんぷ)も聖者(せいじゃ)もだれもが平等に阿弥陀仏の浄土「極楽」に往生できるという教えを聞いて、多くの出家者が法然上人を慕って弟子入りして参りました。また貴族や武士、さらには農民や町人などの一般庶民までが、幅広く法然上人に厚く帰依しました。往時の人々にとって法然上人の教えはまさしく「生きる力」であったのです。
このように、当時の人々に生きる喜びと勇気をお与えになった法然上人は、お亡くなりになるまで終生「墨染(すみぞめ)の衣(ころも)」で通され、また自らの寺を持つこともありませんでした。もちろん「世間の名声」ともまったく無縁の存在でした。
「法然は当代切っての智慧者よ」と称賛された深い仏教理解、しかのみならず、逢(あ)う人の魂を深く揺り動かして離さない、上人特有のお人柄で、数え切れないほど多くの人々を教化された法然上人は、このような日々の内に、80歳の天寿を全うされるまでの間、休むことなく教化を続けられ、建暦2年(1212)正月25日、大勢のお弟子方や信者の人たちに見守られながら、お浄土へ帰っていかれました。
法然上人のおしえ
<念仏(ねんぶつ)の元祖(がんそ)>
念仏を称えて阿弥陀仏の浄土に往生する――この教えは、わが国に初めて仏教が伝えられた時点で、既にもたらされています。しかし、それと法然上人の説かれた教えとでは、どこが違うのでしょうか。なぜ法然上人を「念仏の元祖」と呼ぶのでしょうか。
法然上人以前の教えでは、阿弥陀仏の救いに与(あずか)ろうとすれば、自らの力(これを自力(じりき)といいます)を拠(よ)り所(どころ)に、「此(こ)の岸(きし)」より「彼(か)の岸(きし)」に向かわなければなりませんでした。これに対し、法然上人は、阿弥陀仏が「彼の岸」から、私たちの居る「此の岸」に出向いてくださる(これを来迎といいます)、とお説きになりました。ここが全く異なる点です。
法然上人以前の仏教指導者は、心を統一して阿弥陀仏の姿や浄土の光景を完全に思い浮かべるという修行が必要な条件であり、念仏はそれを確実にするための手段と位置づけました。
法然上人はそうではありません。念仏が「全て」でありました。それは、阿弥陀仏の「人(ひと)と為(なり)」を「本願(ほんがん)成就(じょうじゅ)就の仏(ほとけ)」ということに見出されたからです。
<阿弥陀仏(あみだぶつ)の本願(ほんがん)>
阿弥陀仏は、まだ法蔵(ほうぞう)という名の菩薩(ぼさつ)(修行(しゅぎょう)僧(そう))であったとき、生きとし生ける者(これを衆生(しゅじょう)といいます)を救うために、四十八(しじゅうはち)の「誓(ちか)い」(これを別名「本願(ほんがん)」といいます)をお立てになりました。その「誓い」とは、
私が仏となるからには、ありとあらゆる衆生を救い取るために、四十八の本願を実現するであろう。それが出来ないようなら、私は誓(ちか)って仏(ほとけ)とはならない。
というものです。
そしてそれを端的に示しているのが、第十八番(だいじゅうはちばん)の願(がん)です。
私が仏となったときに、私の名を呼ぶ者が私のも許(もと)へ生まれてくることが出来ないようなら、私は誓って仏とはならない。
かくして法蔵菩薩は、艱難(かんなん)辛苦(しんく)の苦行を積み重ね、今から十劫(じっこう)の昔に阿弥陀仏(あみだぶつ)という名(な)の仏(ほとけ)に成られました。言い換えれば、法蔵菩薩が阿弥陀仏という名の仏の位にお就きになったということは、四十八の本願――全分(ぜんぶん)他力(たりき)の救済(きゅうさい)の原理(げんり)――は、見事に成し遂げられたということに外なりません。法然上人は、ここに着目されたのでした。
<救済の原理としての念仏>
第十八(だいじゅうはち)願(がん)は、「仏となったときの我(わ)が名を呼ぶ者を救い取ることが出来ない限り、私はけっして仏とはならない」と誓われたものでありました。そしてその願が見事果(は)たされ、阿弥陀仏という名の位にお就きになったということは、「名前を呼べば、私たちは誰であろうとその仏(ほとけ)の許(もと)へ生まれ往(ゆ)くことが出来る」ということであります。そしてその「名前を呼ぶ」ということが南無(なむ)ということであり、「名前」とは阿弥陀仏ですから、私たちはただただ「南無阿弥陀仏」と称えさえすれば、阿弥陀仏の許へ生まれて往けるのです。これが、法然上人の「お悟(さと)り」です。
従って、「念仏を称えることは、阿弥陀仏の本願に順(じゅん)ずること」に外(ほか)ならず、それゆえ法然上人は、「念仏を称えさえすれば、修行の有無に関係なく、みな平等に阿弥陀仏の救いに与(あずか)ることが出来る、すなわち浄土往生が出来るのだ」と説かれたのです。こういう見方は、今まで誰も説かなかったことでした。法然上人が「念仏の元祖」と呼ばれる所以(ゆえん)は、ここにあります。
ですから、法然上人のお勧めになるお念仏は、それを称えた時に初めて救われるというのではありません。我々(われわれ)はもとより救われた身なのです。その救いの謂(いわ)れをしっかりと胸に畳んで、喜びと報恩の中に日々を送って行くこと、これが法然上人の説かれたお念仏の教えであります。
<法然上人の御詠>
『月影(つきかげ)の至(いた)らぬ里(さと)はなけれども 眺(なが)むる人(ひと)の心(こころ)にぞ澄(す)む』
月影とは月の光のことですが、月が空に上って、その光があちらだけを照らし、こちらを照らさないというような不条理(ふじょうり)なことは、決してないにも拘らず、月を背にしていると、自分が今、月の光を真(ま)っ向(こう)に受けているということに、なかなか気が付かないものです。しかしそれに気が付いて、あらためて月を仰ぎ見るとき、まさしく月の「光」がその人の心の中に澄みわたる――というのが、このお詠(うた)の意趣(いしゅ)ですが、これは飽(あ)くまでも譬(たと)えであります。その本旨(ほんし)は、「阿弥陀仏の慈悲の光明も、月の光と全く同じように、だれかれの別(べつ)なく、平等に注(そそ)がれている。なのに中々そうと知ることはない。しかしそれに気が付けば、『そうだ。実はわが身は、ちょうどこのように阿弥陀仏の慈悲の光明に照らされている身であるということがよく分かることだ』」ということであります。
<結び>
もしも、法然上人のこのような念仏の受け止め方がなかったなら、つまり、法然上人以前の浄土教のままであったなら、阿弥陀仏の救済に与(あずか)れるのは、極めて一部の人たち――自らの力・修行を拠り所として、覚(さと)りの世界に到達できる人たち――だけであって、それ以外の圧倒的多数の人々は今もって、只々「路頭(ろとう)に迷(まよ)っている」ことでしょう。
されば、法然上人がこの世にお出ましになったからこそ、私たちはこの身のままに往生できる道に出会うことが出来たのです。また私たちは、この煩悩にまみれ切った我が身が、居ながらにして往生させて頂けると理解できたなら、どのような心持ちで日々を送れば可(よ)いのでしょうか。
この文章をお読みいただいて、皆さま方が念仏(ねんぶつ)を喜(よろこ)ぶ、真(しん)の念仏(ねんぶつ)行者(ぎょうじゃ)とおなりくださいますことを、心より念願いたしております。
(専修寺/岸野亮哲)